政府は、この8月から景気の現状について、「弱含み」という表現を用いて、景気後退局面に入ったことを認めています。これによって2002年2月から6年間以上続いてきた、戦後最長の景気回復期に終わりを告げたことになります。
6年間という景気回復の期間は、まれにみる長い期間です。しかしその景気回復とは一体何だったのでしょうか。
通常、景気がこれだけ長く回復していけば、我々一般家庭においても、給料が上がって、生活が豊かになるなど、実感できる効果が出てきます。しかし今回はそのように実感に大変乏しいのが実情です。
この6年間の間に、確かに大企業を中心として企業セクターにおいて収益が伸びるという傾向は見られましたが、それが一般家庭の所得にまで波及せず、暮らしの現場での景気回復の恩恵は感じられません。
働く現場でも、非正規雇用が急増するなど、不安定な雇用状況が進みました。まさに、格差が拡大したわけです。
今回の景気回復は一体何だったのだろうか。景気回復の実感が得られなかった原因はどこにあるのだろうか。突っ込んだ分析が必要です。
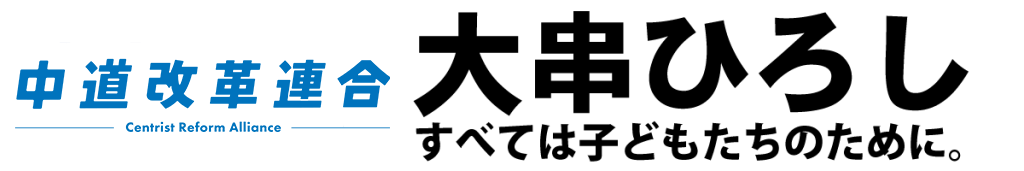


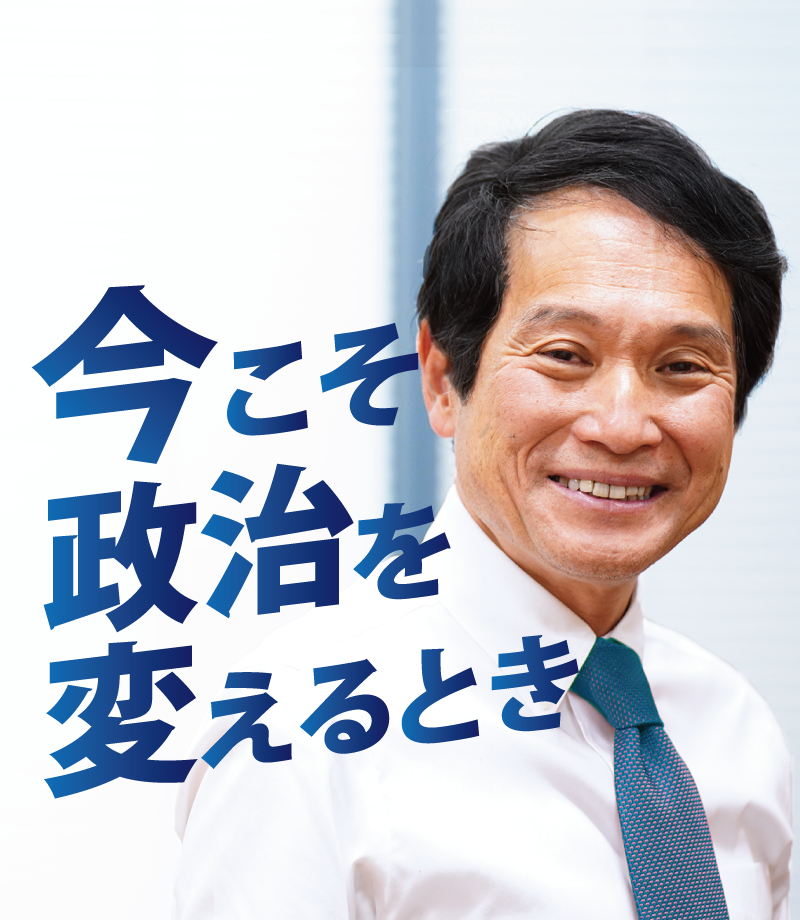

コメント