100年に1度の経済危機という名のもとに、いろいろ懸念を抱かざるをえない政策が取り上げられようとしています。先日指摘した政府紙幣もその一例。
さらに今、経済産業省から、銀行のみならず一般企業にも、最終的には政府の財政負担になる形で資本注入し救済を行おうとうする法案が用意されています。
これも「100年に1度」の名のもとに。もちろん雇用や国内経済への広い影響などの観点からある一定の条件下で、一般企業にも政府財政負担による出資が行われるという政策が全て間違っているとは思いません。
しかし、今提案されている仕組みを見てみると、どの主体が、どのような基準で、「この企業は救う、この企業は救わない」という判断を下すのか、問題なしとは言えません。
言わば「閻魔大王」役たる主体は日本政策投資銀行や経済産業省とされています。また判断の基準は今のところ明らかではありません。このような仕組みの結果、政治の圧力などが働いて、その中で非常に不公平、不透明な形で、救われる企業と救われない企業とが混在していくのではないかという懸念があります。
私は、一定の中立性を担保し、専門性と透明性を確保した主体、仕組みを作っていくべきだと思います。かつて作られた「産業再生機構」のような形もひとつの参考事例となるでしょう。
そう思いながら今日の日経新聞を見ていると、「自民党、ゆうちょ銀行が個人・法人融資を行うことを認めることも検討」といった趣旨の記事が載っていました。これも理由は「現在の経済危機の中で、民間金融機関では十分資金需要に応えられない」ということだそうです。今のゆうちょ銀行に個人・法人融資を拡大していくだけの態勢が十分か、政府が100%株式保有する中で妥当なのかといった点はしっかり検証されなければなりません。
「100年に1度」の経済危機。大胆な政策が求められます。しかしどこまでが本当に求められる政策なのか、厳密な分析、判断が必要です。
(写真は今日の事務所での、有明海弁護団のみなさんとの打ち合わせの模様です)
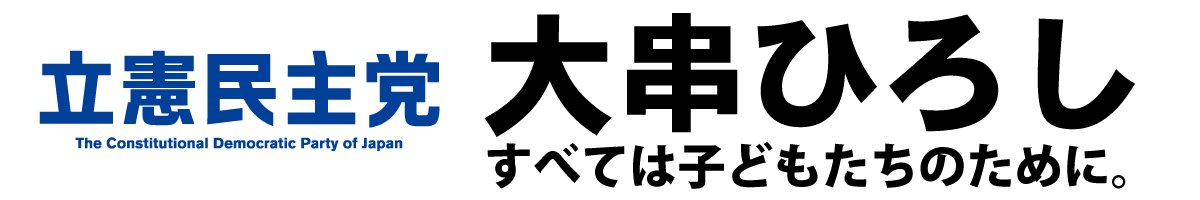

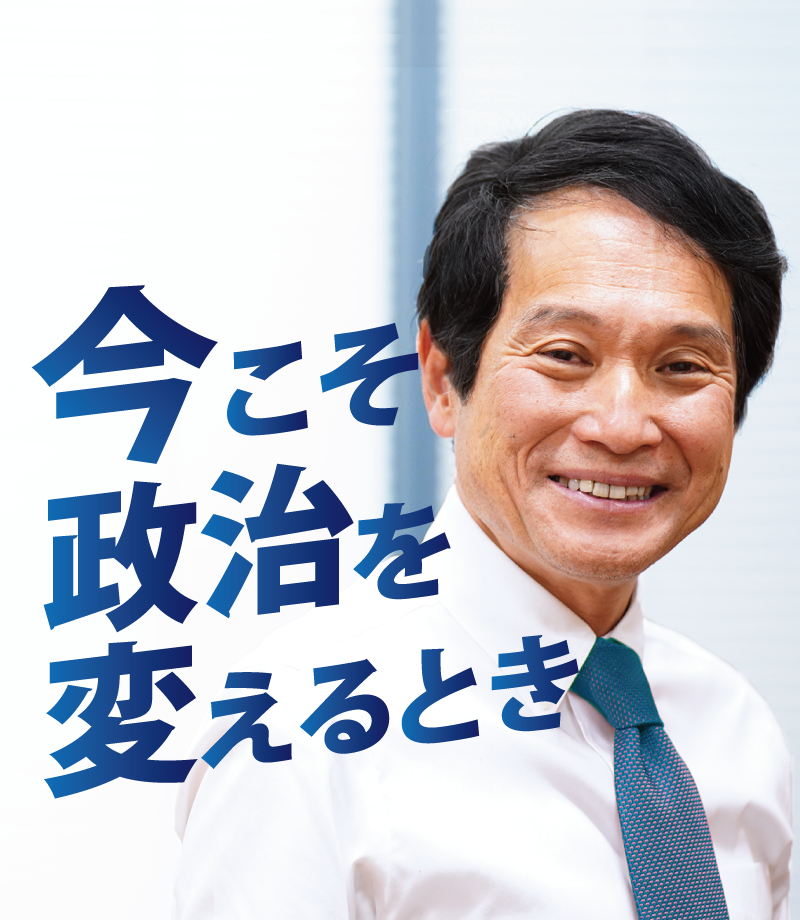

コメント
コメント一覧 (3件)
先生の懸念の通りと思います。資本が不足しているということは、それは、市場がその企業に対して経営上の一層の努力あるいは市場からの退出を促しているのかもしれない。それを、政府の判断で資本注入するということになれば、そうした市場の判断を歪めかねない。一時的にその企業が延命しても、産業構造の転換が遅れたり、投下した資本が毀損することになるかもしれない。投下資本の毀損は、経済対策の信用保証枠の拡大で実際に懸念されていることだ。政府の判断は、市場の判断より賢明なのだろうか。さらに、政府の判断には、政治的な思惑が入りかねない。こうした議論は、できれば経済危機下ではなく、平時に是非議論しておくべきことだ。昨今のような経済状況だと、「かかる緊急時に何を言う!」と、なし崩し的に政府関与が拡大し、それが正当化、常態化しかねない。
おっしゃる通りで、インフレの時は在庫価格が上がるのでどんな企業でも利益を出せます。デフレの時には効率性の低い企業は淘汰されます。こうして適者生存して社会全体の効率性が保たれます。
ところが、インフレ時の利益は株主と経営者が丸取りし、デフレ時の損失は国民の税金で尻拭いしてもらうでは、大量のモラルハザード不適者企業の重荷に国民は押しつぶされて、新しい創意工夫も時代への変化適応もできません。絶滅への道になってしまします。
早く政権交代しましょう。新しい創意工夫と時代変化への適応の一例です。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090206/plc0902060254001-n1.htm
政府紙幣は当初の元締めがおさえこまれて安心したのですが、別方向でくすぶりそうで心配です。郵政民営化を叫んで人気を博した人、見直しを言って嵐を呼びたい人、大樹と全逓は大丈夫でしょうか? 途端返ったんじゃないでしょうね?
数日前のエントリー関連で恐縮です。麻生内閣と反目している谷人事院総裁が、官僚上がりで渡りしまくりな人であることが産経で攻撃されてますね。さらに残り2人の人事官ポストの内1つは、過去50年大手マスコミOBの指定席となっているそうです。歴代人事官を輩出したのは朝日毎日読売日経NHK。報道したのは産経のみ。わかりやすいですね。これで天下り廃止なぞ出来る訳ありません。ご存知の方も多いでしょうが為念まで。