「骨太の方針」 これをめぐって、与党が揺れました。2006年に小泉総理が退任する直前に作った「骨太の方針2006」。この中に、今後の財政運営の指針が示され、毎年社会保障費を2200億円削減することが書かれました。その結果、医療、介護などを含む、国民への福祉サービスは大きく抑制されてきています。この点が議論の中心でした。
そもそも、「骨太の方針」とは何か。これは橋本総理の下で行われた中央省庁改革の中で作られた機関、経済財政諮問会議において作られるものとして登場しました。
「総理の意思決定を支える知恵の場、総理の諮問機関」として、総理・官邸主導の意思決定を支える機関としてこの経済財政諮問会議は作られました。
その名前、「経済財政」。 こうなっていることで、それまで財務省が独占していた財政政策まで、経済財政諮問会議が、あるいはその事務局である内閣府(元の経済企画庁)が手を突っ込んでくるのではないか。
それを懸念した財務省は、経済財政諮問会議の役割探しに奔走しました。財務省の権限たる予算編成にまで首を突っ込まれないように。その結果生まれたアイデアが、「個別の予算編成作業は財務省の仕事だけれども、その代わりに経済財政諮問会議においては、総理の意思決定にふさわしい『骨太』な方針、財政政策の大まかな方針を示してもらおう」というものでした。
この方向で財務省も各所に根回しをし、「骨太の方針」に落ち着いたわけです。このように、その生まれるところから、「骨太の方針」は、そして経済財政諮問会議は、縦割り行政の影響下にあったと言えます。
経済政策を作る上での政府の仕組みとして、「骨太の方針」・経済財政諮問会議がどのような役割を果たすべきなのか、その存在が本当に今のままの形で必要なのか、それが機能を果たすためにはどのような環境が必要なのか。今後十分な分析が必要です。
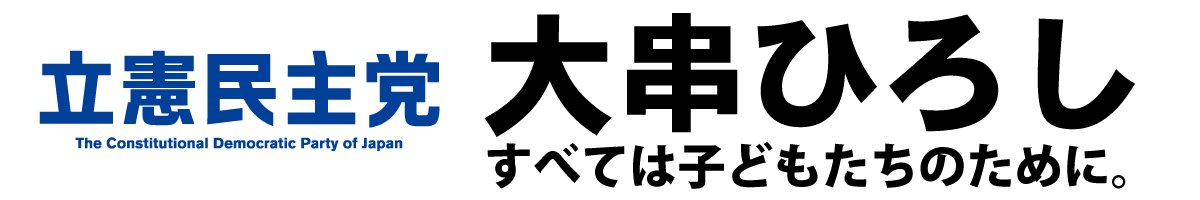

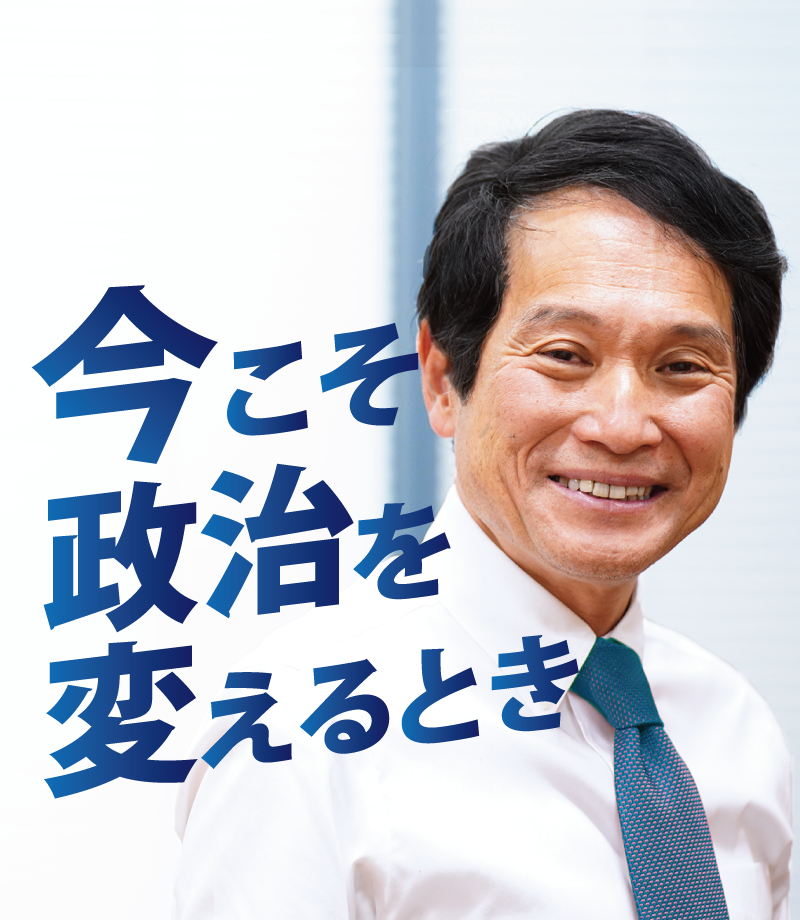

コメント