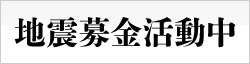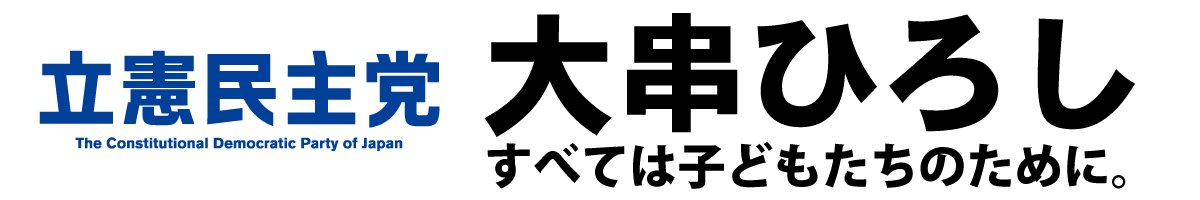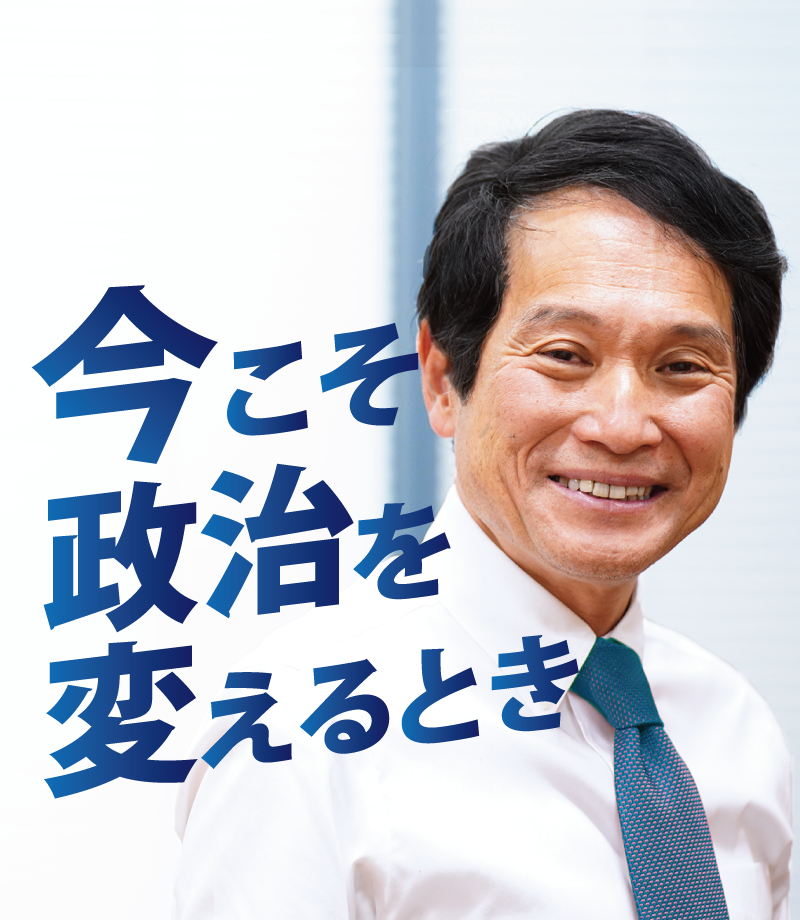今回は、三陸海岸を岩手県の方に向かって北上し、南三陸町を中心に見てきました。
南三陸町は、津波被害のことさら甚大であったところ。海岸沿いの町のほとんどが津波で流されました。町役場はあとかたもなく、その隣にあった鉄筋の防災庁舎も、まさに鉄筋だけが残っています。町長さんも、そのてっぺんの鉄塔につかまって何とか津波に飲まれるのを防いだという町。
さらには、防災担当であった若い町職員の女性が、津波の直前まで町民の避難を促すためにマイクを握り、自らは津波被害に飲み込まれてしまったという、「天使の声」の町です。
津波による被害のすさまじさは、言葉ではあらわせません。高校、中学校、小学校が高台に位置する町であったので、そこに向けて町民の皆さんが避難する目標があったということが幸いでした。しかし津波に流された町の中心部はあとかたもありません。
南三陸町の近隣の仮設住宅にも行ってきました。「ここに入れてもらって本当に有難いです」とおっしゃる方、「家族も亡くなりましたので・・・・」と言葉少なく語られる方、それぞれの状況を目の当たりにして、継ぐ言葉もありません。
がれきの処理の遅れは否めません。それはどこに課題があるからなのか。確かに、市町村や県といった地方自治体を一義的な対応者としているところに問題があるのかもしれません。
これだけの規模の災害ですから、国直轄という形でのがれき処理が必要だという声に説得力を感じます。さらに言えば、国直轄でがれき処理を行っていくとすると、省庁縦割りの問題がその障害となっていく可能性も感じられます。そのような点から、復興庁といったような一元的な組織の必要性も感じられました。
これらの思いをしっかり胸に抱いて、これからの復興基本方針、第三次補正予算案作りに臨んでいきます。