今日は、午前中、佐賀県精神障害者家族会連合会の総会に参加してご挨拶。(写真)
その後、電機産業の場で働く仲間の集い、「電機佐賀改革フォーラム」にて国政の報告をさせていただきました。
午後は、昨日に引き続き、故大串賢治・元自治労佐賀県本部委員長の葬儀に参列。その後、佐賀市内で支援者のお宅のお悔やみに訪問したあと、夕刻は事務所で打ち合わせ。
夜は、小城市内の支援者の方々と懇親会のあと、夜遅くなりましたが、大町町の知り合いのお宅での三夜待に少々顔を出させていただきました。
さて、「消えた年金」問題。週末に地元で歩き回っていても、あちこちで皆さんの関心の高さがわかります。
皆さんの関心の焦点は、「社会保険事務所に確認に行くときに、自分たちが領収書などの証明を示さなければ救われないのか」という点。
この点について、今の政府の態度は基本的には年金受給者側に「立証責任」があるという立場です。これが受給者には大変なことなのですが、政府はそのために「第三者委員会」を作って、そこでどの程度の立証がなされれば受給者が救われるのか裁定するとしています。
しかし、どのような根拠でこの第三者機関が作られるのでしょうか?法律の根拠もないのに、この第三者機関が「この受給者は救ってよい」「この受給者はダメ」などという判断を行っていいものでしょうか。
さらに言えば、この第三者機関、今のところ、厚生労働省ではなく、総務省に設置する方向のようです。しかし、総務省設置法のどの条文に、総務省においてこのような機関を置けることが書かれているのでしょうか?
もっとも肝心な問題なのですが、まさにここがはっきりしていないのです。
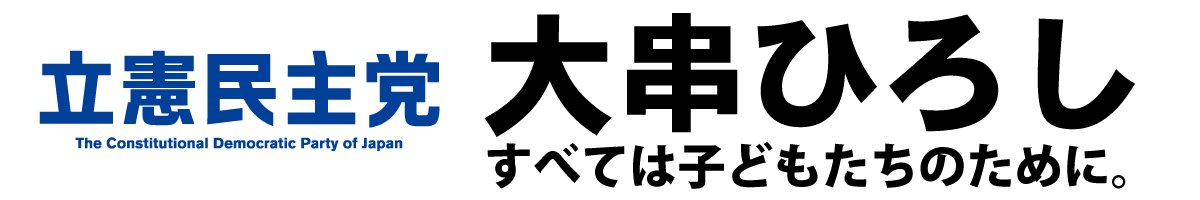


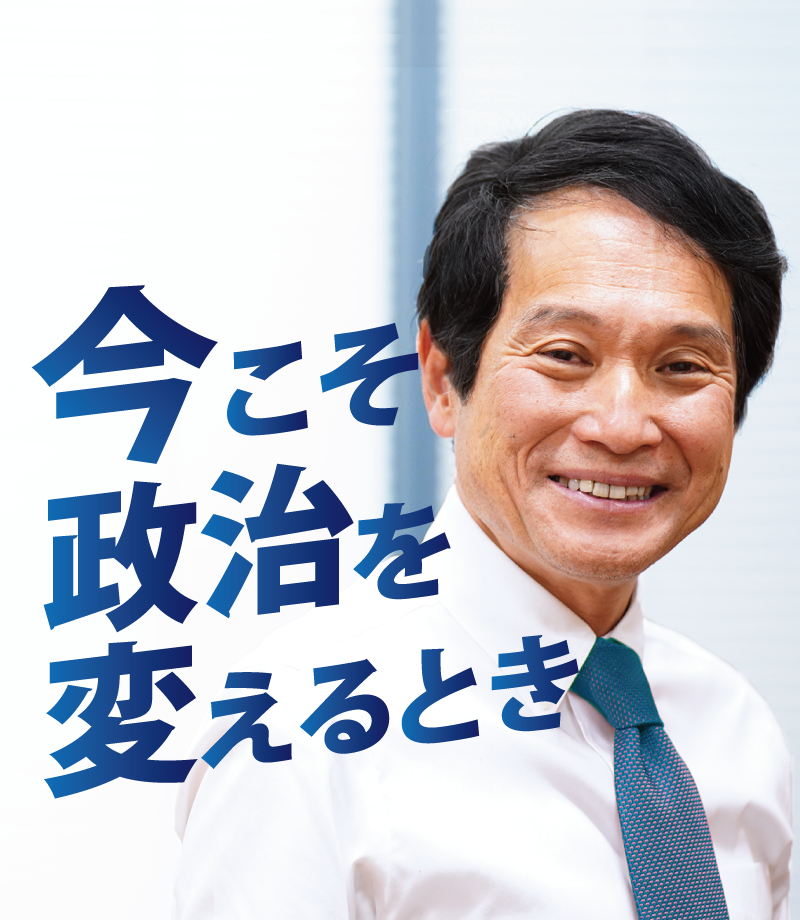

コメント
コメント一覧 (6件)
120 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2007/06/10(日) 13:57:42 ID:xmSZxZaC
(ノ∀`)アチャー
自治労が社保庁を守るために民主党にリークして問題化させたデマゴーグ
by 花田@たかじんのそこまで言って委員会
「消えた年金」基礎年金番号5000万件の問題は、このブログにもたびたび書きましたように、長妻昭議員をはじめとして、多くの議員が何年もかけて、社会保険庁から収集した情報の結果やっと明らかになってきた事実です。それは決して「自治労が社保庁を守るために民主党にリークして問題化させたデマゴーグ」ではありませんので、ご理解をいただければと思います。
まず始めに私は民主党の支持者である事をお伝えします。ただし現状は無党派に
スタンスを移していると言っていいでしょう。
実は私の嫁ですら(不謹慎な表現ですが)疑問を持ち始めています。
被害者のデータや状況を入手できるのは判るとしても、なぜ公開されていない
(政府が公開していない)社会保険庁内部の情報を民主党だけが入手できるのか
と言う部分です。
政府が隠している可能性は有りますが、度々民主党の質問で「事実」が露呈し、
信用が失墜する現状では隠しているほうがダメージが大きいのに何故隠し続ける
のか?と言う当然の疑問です。
それに加えて早急に救済すべき人々が居る場合は根本的対策に先立ち暫定的な対
策を打つのが当然だと思えるのに、それに反対するのはなぜか?という事です。
DBにも台帳にもデータの存在しない人々の救済はどうするかに関しては「政治
的解決」しかないでしょう。
現状提示されているのは与党案のみで民主党案は法案読んでも見えてきませんし、
野党党首質問での小沢代表の説明が民主党案だとしても詳細は何一つ判りません。
個人的にはある結論に達していますがここでは書きません。
もっと目に見える政策を提言できる党になって頂きたい物です。
頑張んば、いかんバイ 民主党―――!
社会保険庁の不祥事って、監督する立場の原因もありますが、それより仕事をしない職員の体質が一番悪いんじゃないの!!
ところで、
民主党って、自治労の組織票で、支えられているんですか?
だとすれば、社会保険庁職員を擁護し、政府が悪役だとするイメージ操作を繰り返す民主党の戦略が合点できます。
旧国鉄が民営化されてJRになり、非常に使いやすくなったと思っている自分ですが、社会保険庁も働かない不謹慎な職員は排除して、勤労意欲に燃えている職員を残して民営化した方がいいんじゃないかな。
コメントをありがとうございます。まず、「社保庁内部の情報を民主党が入手」ということはありません。「消えた年金」問題については、すべてこちらから社会保険庁に問い合わせ、また国会の場で質問するなどして出てきた情報を積み上げた結果であり、すべて公開情報です。内部情報をもとに調査しているということはありません。また、今般民主党は、年金の記録を調査するための法案を以前から出しています。長い議論を積み重ねて作った法案であり、政府・与党のように2日で作った(そして半日の審議で衆院を通過させた)というものではありません。