諫早湾干拓事業について、今でも、先に農水省が佐賀地裁の判決に対して控訴を発表した際の、「農林水産大臣談話」をどう理解すればよいのかということを尋ねられることがあります。これは開門に向けて進んでいるものと評価していいのかどうか、と。
以前にもこのブログに書きましたが、私は、開門に向けて進んだとは言えないと思います。なぜなら、第一に開門のための環境アセスメントをするとなっていますが、これはあくまでも環境アセスメントの結果を踏まえて開門してよいかを考えるということです。ですから、若林農水大臣は記者会見において、「環境アセスメントの結果、開門しないという結論になることはある」と趣旨を明確に答えています。
第二に、私はこちらの方がより問題が大きいと思うのですが、「関係者の同意を得て検討する」とされていること。すなわち諫早湾干拓事業において利害関係を有するすべての方々(自治体)の了承がなければ、開門ができないということを、「明文化」しているということです。
今までは、どこかの誰か((自治体)が反対した場合には開門できないということは明文化はされていませんでした。ところが今回は、「農林水産大臣談話」というペーパーの中に、明らかに書かれています。これが意味することは、例えばひとつの自治体でも開門に反対したら開門できない、すなわち開門に対して「拒否権」を文章に書いて認めた、ということになります。(実際に、長崎県知事もこの点に言及しています)
官僚が盛り込んでくる、このような数文字の言葉。これが極めて重要な意味を持つことがあります。官僚は、このようにさりげなく、それでいて重大な意味を持つ言葉をさらりと文章に入れ、自分たちのよいようにあとから事が運べるようにする、高度な技術を持っています。
「悪魔は細部に宿る」という言葉もあります。 政治家はまさにこのような細部に潜む、官僚の技巧を見抜き、流されないようにしなければなりません。
今回の「農林水産大臣談話」、まさにこの細部が問題なのです。
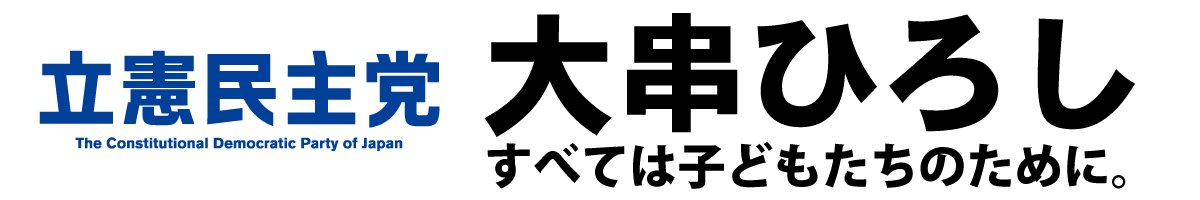


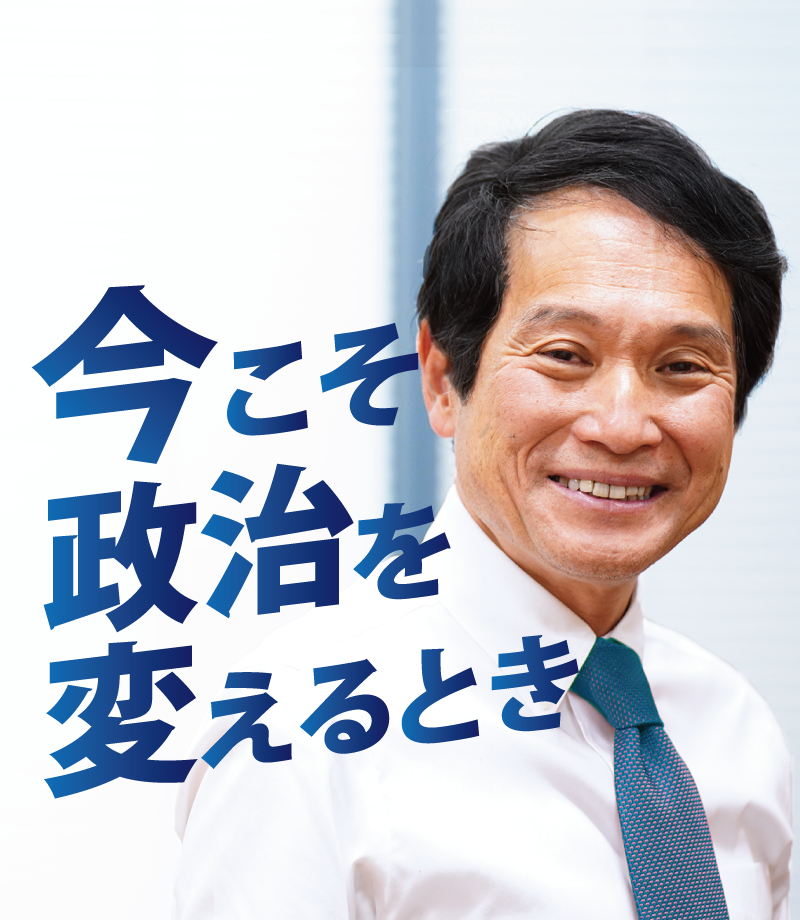

コメント
コメント一覧 (1件)
そうですね、官僚の文言については、与野党議員が同じ指摘をしています。
問題は、基本的に国側は、自分達のした失敗を認めないというスタンスです。企業だろうが人間だろうが、失敗はします。失敗を認めないと裁判という争いになります。すれば、時間が経過します。薬害肝炎も早期和解が成立したので、生存者が多かったですが、争いを続ければ、遺族補償になるという悲惨な現実になります。ある意味、北朝鮮の拉致も同じで、平行線のままだと拉致被害者は亡くなってしまいます。
諫早湾ですと、漁業関係者の収入源、年齢層を考えれば、判決で開門になってもその判決に意味を持たない、喧嘩で勝ったという意味しかなくなります。同様に環境も壊れるのは速いですが、回復には時間が掛かります。
基本的に官僚が悪いという風潮がありますが、この大事業は、政治家主導でしょう。計画の予算枠を取っておき、農地確保の意味がほとんどなくなっても、組織票、地元利益誘導のために事業を行う必要があった。特に長崎県ですと産業も無いですし、事業による経済効果の期待が高かったと思います。事業誘致、宣伝を国会議員は、選挙で勝つために行う。後は、知らん。官僚が悪い。というのもおかしく思います。官僚も派遣労働者と同じく物扱いですね。