世界の原油価格について、高騰の要因についてよく尋ねられます。中国・インドなどの大量消費が見られるようになったという構造的要因と、その他世界の投機マネーが原油市場にどっと流れ込んでいるという投機面での要因があると思います、と答えています。
その投機的要因について、ここまで原油価格が上昇し、国内物価を全般的に押し上げ、経済へのマイナス影響を大きくしていることに鑑みると、この投機的要因については何がしかの方策を緊急に採らざるを得ないという思いを強くしています。
もちろん、自由な市場の動きに対して政府・行政があまりに規制を行うことは避けるべきです。「市場」の方を信じるか、「政府」の方を信じるか、と私に問われれば、どちらかと言えば市場の方を信じる気持ちが強いと言わざるを得ません。
しかし今回の原油市場において見られる価格の上昇は、明らかに市場がうまく機能していないことによるものだと思います。いわゆる「市場の失敗」であり、「投機バブル」です。
そうであれば、市場が適切に機能するようにするために、市場をできる限りゆがめない形での規制は考えるべきだと思います。
米国が、金融株のカラ売り規制を行ったこともあり、これに連動して原油価格はこのところ低下傾向を見せています。
市場の自律的な動きは大切にしなければなりません。しかし市場の失敗が起こったときに、適切な内容のコントロールを行うこと、これもまた政府の機能として求められていることだと思います。
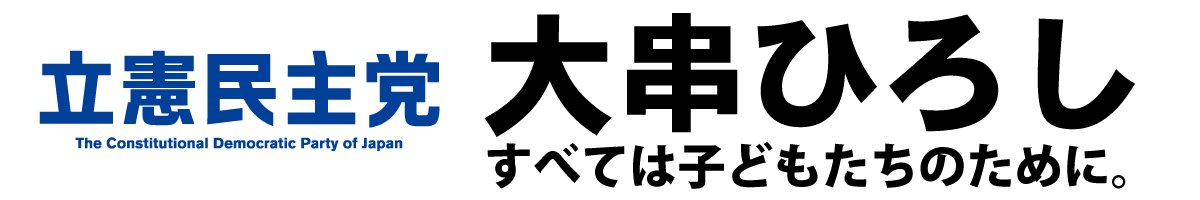


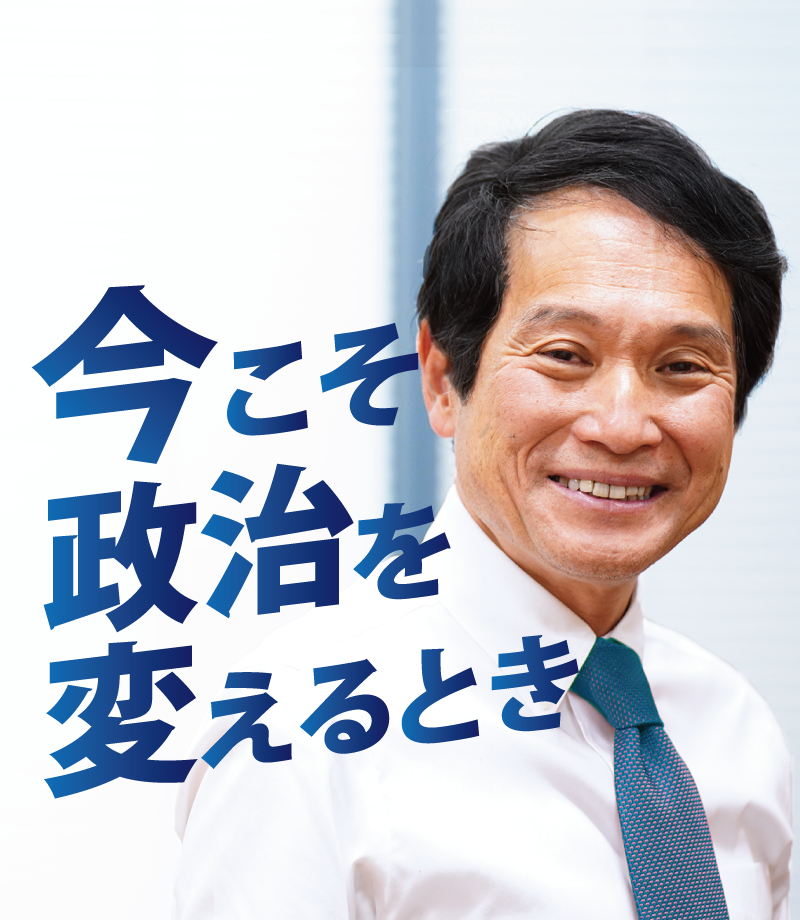

コメント
コメント一覧 (1件)
あのー、原油先物価格は、実取引に関係ないですが、実質、連動で商いされています。ヨーロッパだと原油関係の税率を下げるなどして対応しています。フランスのサルコジ大統領は、ブッシュ大統領に強く対応を求めました。ブッシュ大統領は、石油メジャーの支援を受けているし、大手金融も海外から支援、増資を行っています。決算発表と投資資金(金余り)と会計の密接なからくりが原因です。投機的要因を解決するのは、一国家議員では、絶対無理です。首相クラスでも厳しいでしょう。アメリカの大統領クラスで、若干、影響力があるくらいでしょう。
年金基金の原油先物投資の制限、大口取引の監視、公表などの噂が、影響しています。確かに株価の下支えによる資金の横流れ防止や公社2社の救済の影響もあるとは思います。
実需に関して言えば、あのアメリカでハイブリッドが急増、先進国では、石油消費量が伸びる事は無いでしょう。中国、インドでは伸びるでしょうが、中国、インド等ではドル安傾向です。他のアジアだとドル高でダブルパンチです。つまり、景気減速、原油消費の落ち込みを招いています。