報道に、「金融庁は今後の検査の際、銀行が中小企業に対して積極的な融資ができる態勢になっているかどうかについても重視する方針」という趣旨のものがありました。
これまで、監督・検査というのは銀行が不適切な融資を行って財務状況を傷めるようなことがないようにという「財務の健全性・リスク管理態勢」や、あるいはいろいろな法律を遵守した業務運営になっているのかといった「法令遵守態勢」といった観点から行われてきました。
中小企業に対して銀行がしっかりとした審査を行って、将来性のある中小企業に対して積極的に貸し出しを行うことは、銀行の持つ機能として十分発揮されなければならないことです。日本の場合どちらかというと大企業に対する貸し出しが多く、これは本来の銀行の領分ではありません。銀行が融資を行う先は、中小企業や個人が中心であるのが本来の姿です。その面で、日本の銀行はまだまだ本来果たすべき機能を十分果たしえてはいません。
しかし、銀行がこのような本来の機能を行うことを確保するのは、金融庁による監督・検査という手法を通じてではないのではないかと思うのですが、どうでしょうか。むしろ、銀行が中小企業に適切に貸し出しを行わざるをえなくなるような、競争力のある銀行産業を作っていくことが重要なのではないでしょうか。これは銀行監督・検査と言うよりも、銀行行政という領域の世界の話しではないかと思います。
小さな記事ではありましたが、基本とは異なる重大な方向転換を金融庁は行おうとしているのでしょうか・・・・・
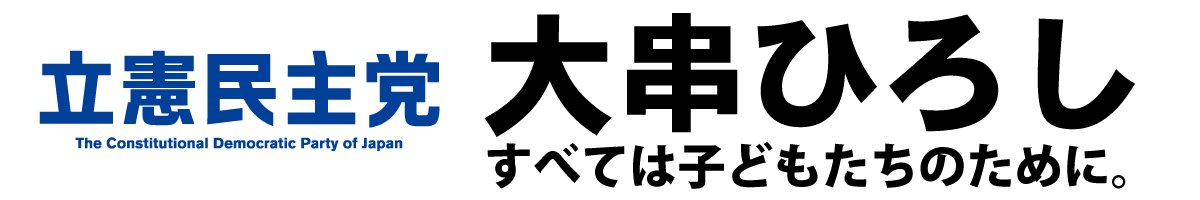

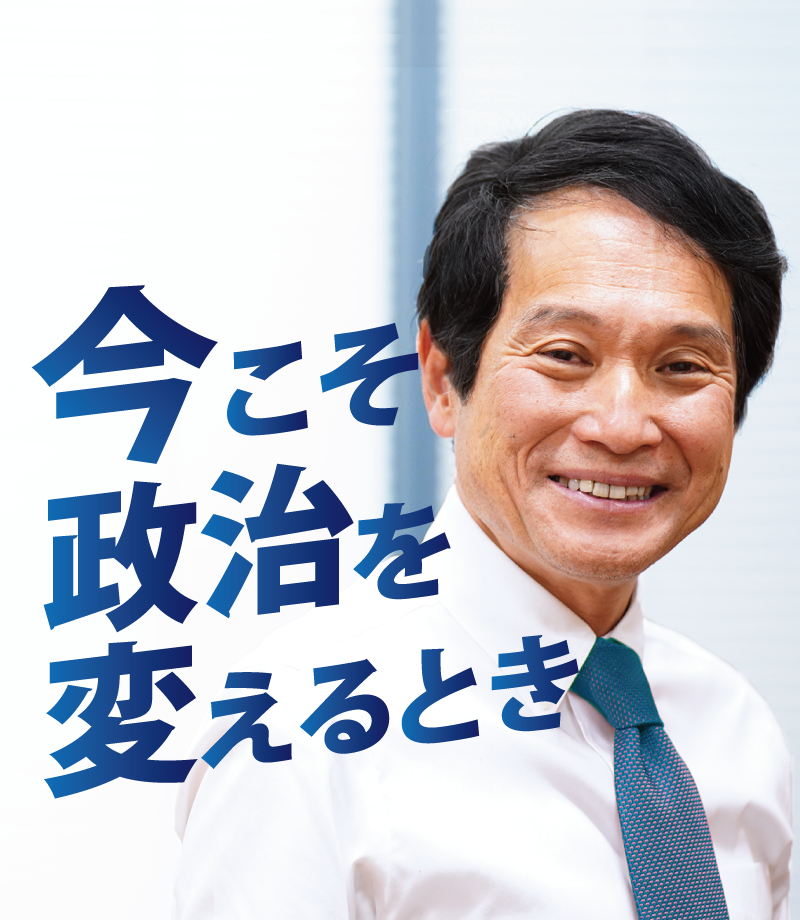

コメント
コメント一覧 (1件)
ご指摘の通りです。銀行業界の歴史、体質を考える必要があります。勿論、金融庁という役割も。日本の銀行業界は、鎖国体質の中、ヌクヌクと育ってきました。そして、バブル崩壊、公的資金投入、低金利政策。大蔵省との関係も深く、守られてきました。次に、体質は、健全体質です。旧破綻銀行、あおぞら、新生銀行、新規参入のソニーなどは、斬新な事をしますが、他は、横並びです。国内の年金運営団体(政府ファンド)と同じで積極運用しません。それは、否定も肯定も出来ませんが、逆に言えばそれでやっていける横並び体質といえます。また、メガバンクも国際競争力や規模で世界に太刀打ちできません。疑問に思うのは、民間の経営であり、不動産・建設は、厳しい競争をし、一定の割合で倒産していく。しかし、銀行は、倒産しない。確かに、国民に与える影響は大きいですが、ペイオフもあり、地方自治体、基礎自治体と同じく、倒産事例が普通に考えれば、増えるのが妥当です。
リスクをとらなくてよい経営は、低金利がもたらしています。基本的に利ざの収入が多く、現在だと貯蓄5割の国民性も助けているのでしょう。リスクを見極め、中小企業でも貸す、リスクに応じて貸し出し金利を変える。運用により収益率をあげるなどが、プロなんですけどね。プロがいなくても、生き残っていけるので、合併によるメガバンク誕生はありましたが、業務の効率化による支出削減、顧客数増、資本金増で終わっているのが、現状でしょうね。