米国の住宅ローン市場発の経済危機に対して、米国政府は、ついに政府系住宅金融会社の2機関に公的資金を入れ、救済することを発表しました。
これによって市場は一息ついているような様子です。しかし、今回のこの救済劇には、私はふたつの問題があると思います。
ひとつは、この公的資金投入のタイミングが遅かったこと。以前にも書きましたが、金融危機への対応の基本は、こまぎれの対応を遅ればせながら行うのではなく、大胆な対応をタイムリーに行うこと。今回は明らかに遅かったと思います。しかしこのように遅くなることはこれまでにもあったことであり、ある程度は予想がつきます。
ふたつめの問題はより大きな問題ですが、両機関のトップに対しては辞任を求め責任を追及したのですが、株主には負担を負わせなかったこと。金融危機への対応の際には、経営陣および株主に対して責任を適切に負わせることは、ある意味雛形となっているのですが、今回米国はこれをしませんでした。
今回のこの対応は、この2公的住宅金融会社に対して、「暗黙の政府保証」があることをはからずも明らかにしました。
米国は、日本の郵政事業に対して、政府による「暗黙の保証」があるとして、これを民営化するべきと主張してきました。しかし自国においては「暗黙の保証」を認めている。
これが国際社会だと私は思います。他国に対しては思いっきり言いたいことを言い、自分の国はまた別。
財務省に勤めていたときに、国際交渉に多く臨んできましたが、結局国際社会は、各国の利害関係、エゴがぶつかり合う場所だと痛感しました。今回の米国の動きもまさにそれを表しています。決してきれいごとではすみません。
日本もその覚悟をもって世界に対して、主張すべきことはしっかり主張していくべきだと思います。
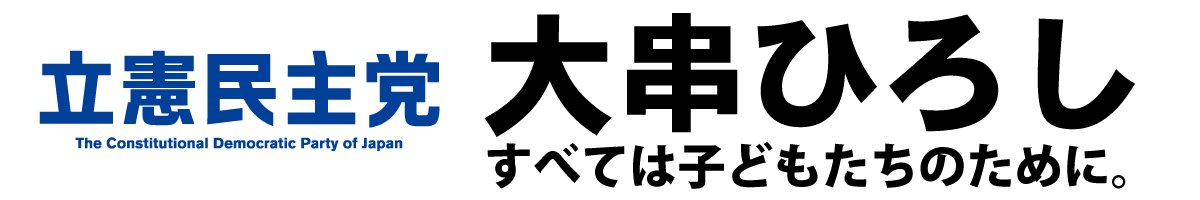

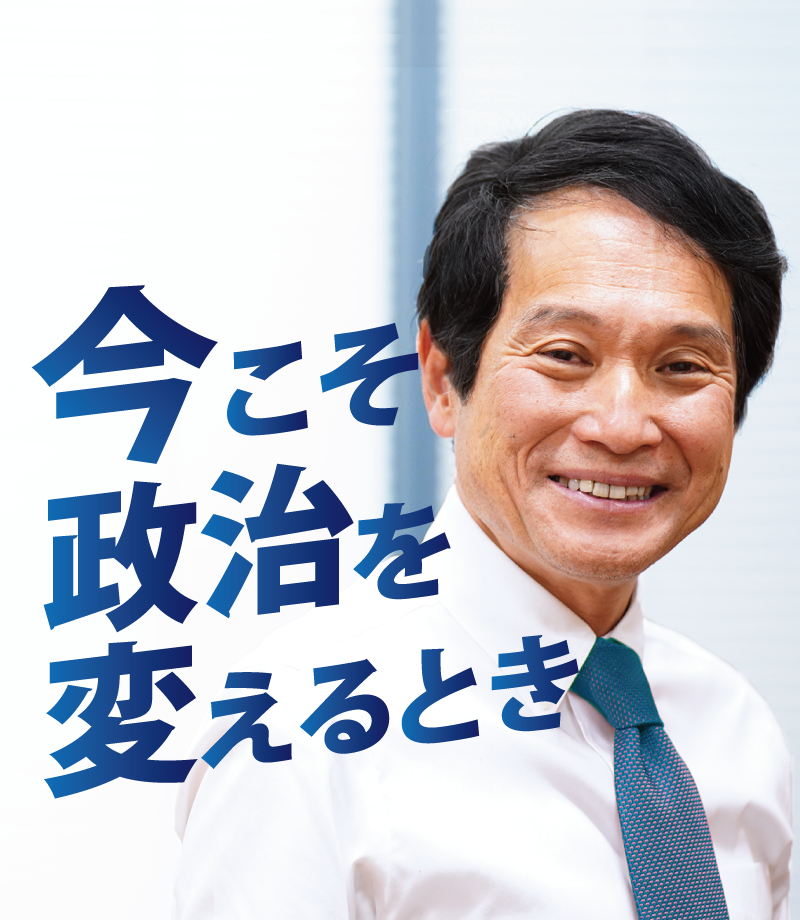

コメント
コメント一覧 (2件)
ご指摘の通りです。環境、核などもエゴですからね。その背景に国連の拒否権などがあります。
グルジア問題が、典型的な例ですね。ロシアの南オセアチア独立支持は、理解できます。グルジア問題では、アメリカ、ロシア、ヨーロッパのエゴ(利権)がぶつかります。パイプラインに支障が出ないようにするためにフランスは動いたのであり、和平が一番ではないでしょう。ロシアは、チェチェンの独立を認めないと主張がおかしくなります。アメリカは、イラク、アフガンの内政干渉の部分もあり、ロシアのグルジア侵攻と似ており批判するにあたるのかということです。
ただ一点、少し違うように感じる箇所があります。それは、日本と比較してでなく、ご自身のスピード感覚と合わないのでしょう。アメリカの対応(金利政策、公的資金投入、民間の不良債権処理)は、早かったように思います。その処理の早さ、地方銀行の倒産の早さは、日本と違います。日本は、不良債権を長期保有し、10年ほど処理に掛かっています。公社2社に対する保障は、日本の金融機関も10兆円ぐらい債権を保有しているらしいので、関係国への配慮、ドルの世界的地位の維持の目論みもあります。中国もかなりの金額を保有しています。
サブプライムは、債権化して世界にばら撒かれた事、アメリカの担保による信用取引の額の大きさにより世界を混沌とさせました。サブプライム、株からの撤退による行き先を失った投機マネーの商品先物への投資。共に落ち着きを取り戻し、沈静化を見せています。ただ、未だに値上げが止らない現実などがあるのも事実です。
株主は株価で十分洗礼を受けております。問題は両組織トップの退職金額ではないのでしょうか。本来なら背任などの刑事責任をうけてもいいくらいのところですね。多すぎます。