米国の証券大手、リーマン・ブラザーズが破綻し、米国金融は深刻さが一層増しています。証券第4位の大手の経営危機に対して、業界からの相互支援があるのか、あるいは政府による支援があるのかといったことが取りざたされつつ、急展開しての破綻であったが故に市場の動揺も大変大きいものがあります。
サブプライムローン問題に関連して、米国の金融に関する政策は漂流しているような感すらあります。
そもそもサブプライムローン問題はなぜ生じ、これだけ大きな問題として拡がるものとなったか。これについては、慎重な検証が必要ですが、私には、基本的な銀行監督上の問題があると思います。
住宅ローンに対して消費ローンまで付加してどんどん貸し付ける金融機関の態度がもとにあり、それによって米国の住宅投資、そして家計消費は著しく膨らみました。しかしそのような貸付を、要注意視できなかった銀行監督のあり方は、大変不備であったと言わざるをえません。
現段階では、先のベア・アンド・スターンズ、そして今回のリーマンと、証券化商品の焦げ付きで損失を出した証券会社の苦境が全面に出てきていますが、今後、中小や地方の銀行などにおける問題が顕在化してくると言われています。その恐れは十分あると思います。
ベア・アンド・スターンズの際には、政府による救済を行い、今回は行わなかったという政策も一貫性を欠きます。(私はベア・アンド・スターンズの政府救済自体が問題ではないかと思うのですが)
全世界に広がる景気急減速の連鎖に、十分な緊張感を持って臨まなければなりません。
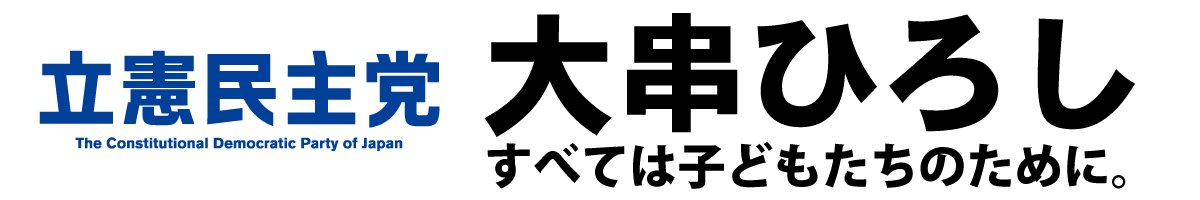


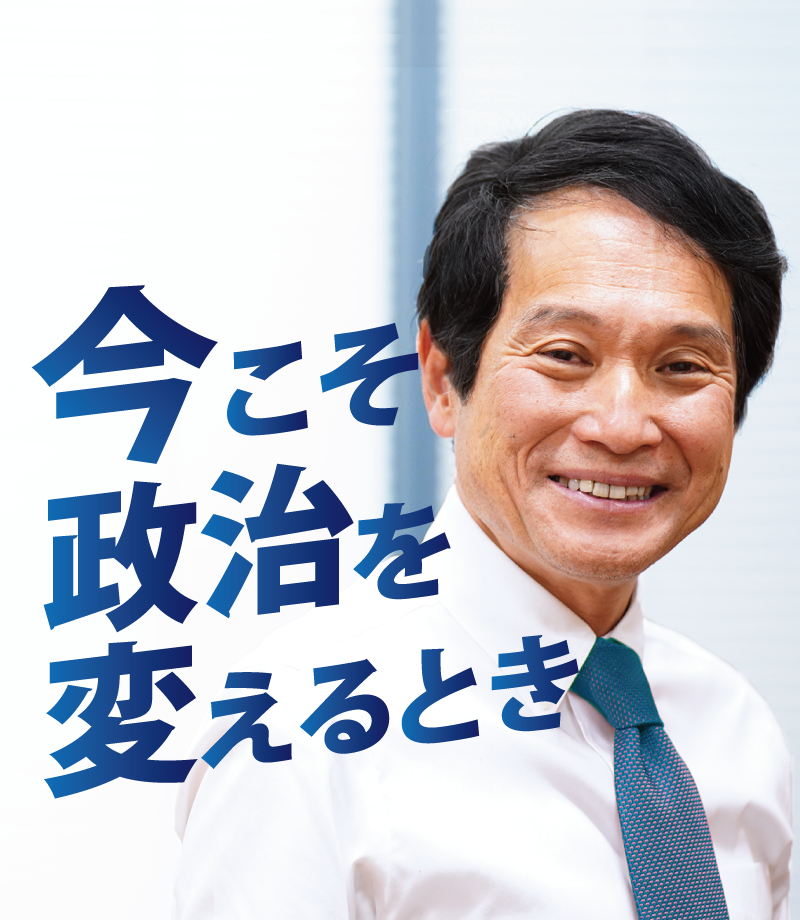

コメント
コメント一覧 (2件)
後、上海の株価急落、ヨーロッパを通した投資金の問題もあります。アメリカ、イギリスは、金融政策により国を立て直した側面があります。今度は、負の部分が大きいようです。
中国も銀行の預金準備率を上げる、公定歩合引き上げ、香港市場の開放などを行いましたが、不動産バブル、消費増を背景としたバブルは、止りませんでした。日本のバブルもそうですが、自由な経済活動と引き換えの部分もあります。難しいのと国民のマインドをコントロールできない側面があります。
メルリンチとバンカメ。AIGなど予断を許さない状況です。政府が救済しなかったのは、金融混乱は一段落し終息に向かう。経済も回復に向かうと思っているのでしょう。
金融危機の事を取り上げられているのは、とても重要だと思います。アメリカの会社の株価が大変下げているのを先週発売の東洋経済(週刊誌)で見ました。心配です。